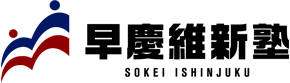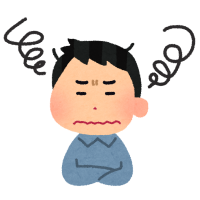
計算ミス克服法 計算ミスを減らして ヤル気を引き上げよう!

皆さんこんにちは!早慶維新塾算数担当の野澤優子(のざわゆうこ)です。
「できた!完璧!」 と自信満々で提出した答案が、バツだらけで戻ってきて、ガッカリ。
直しをすると、単なる「計算ミス」だった…。モチベーション⤵⤵なんてよくあること。
しかし、しかし、その単なる「計算ミス」で、合否が決まってしまうのが入学試験なのです。
今回は計算ミスを減らしていく、克服法をお話しします。
計算ミスの主な原因
計算ミスの主な原因は大きく分けて2つ。
「テクニック」と「書き方」です。

(1) テクニック
① そもそも計算力不足
② 基礎知識を知らない(計算の順序間違い・逆算の間違いなど)
③ 計算の工夫をしない
(2) 書き方
① 自分が書いた文字や数字が汚くて読み間違ったまま計算
② ひっ算の桁や繰り上がりの数の書き間違い
③ 小数点の位置の数え間違い・打ち間違い
④ 途中計算を書かない(頭の中で計算)
お子さまはいかがでしょう?どれかあてはまるものはありましたか?
では次に解決策です。
解決策 (1) テクニック
① 計算力を養う
毎日決めた量の計算練習をノートに行う。
また必ず答え合わせを行い、間違ったところはなぜ間違ったか確認をし、直しを行う。
習慣化してくると、計算力は加速度的についていきます。
同時に計算の順序や逆算の方法も身につきます。これは大前提。
テクニックはここからです。
② 計算の工夫をして 複雑な計算を簡単にする。
■×△+〇×△=(■+〇)×△
■×△-〇×△=(■-〇)×△
例 36×9858+64×9858=(36+64)×9858
=100×9858
=985800
計算がとても簡単になりますね。
特に3.14の円周率がでてくる計算の場合は必ず使うテクニックです。
② 分数を上手に活用して 複雑な計算を簡単にする。
例 2715×30÷2×20÷3
(逆数を使ってわり算を分数のかけ算にすると)
2715×30××20×=2715×10×10
=271500
約分ができて、簡単な計算になります。
割り切れない場合の計算では、分数を使わないと答えが出せませんし、
時計算のように、必ず分数を使って計算する単元もあるので、
分数をうまく活用する計算スタイルにシフトさせていきましょう。
③ 平方数や立方数を覚えて 複雑な計算を簡単にする。
11から20までの平方数や
1から10までの立方数を覚えておくと処理が早くなります。
また、3.14に1~10までをかけた数を覚えるのもよいでしょう。
ポイントは、複雑な計算をいかに簡単な計算に変えるか です。
解決策 (2) 書き方
① 担当の先生が、計算の書き方を説明する。
「丁寧に書きなさい」というだけでは、混乱してしまします。具体的に示さないと、
いつまでも直りません。
② 途中式は必ず「書く」ようにする。
小学校低学年までの習慣からか、頭の中だけで計算しようとする生徒がいますが、
問題が少し複雑になると、混乱して考えられなくなってしまいます。
また、記述式の問題にも対応できるようになります。
③ なぜ丁寧に書く必要があるかを話し合う。(家庭・塾の両方で)
「なぜ受験をするか」にまで話は及びそうです。色々話していく中で、
本物の受験生になれば意識も変わってきます。
ポイントは、丁寧に書く必要性を意識付ける です。

計算ミスを完全になくそうとすると、逆に変な力が入ってミスが増えることがあります。
そういう時は、「何とかしないと…」と思いつめるより、テクニックを再点検。
思いがけないところで、つまずきが発見される場合があります。
また、忍耐強く毎日の計算練習を継続していくことで、
気づかないうち計算ミスは必ず減っていきます。